東京の京橋周辺を歩いていたら、国立映画アーカイブという建物にて『映画雑誌の秘かな愉しみ』という展示をしていたので、ふらりと立ち寄ってみたのだ。

明治時代発行の「活動写真界」の創刊(1909年)から110年だという。

現在も発行されている「キネマ旬報」は、創刊(1919年)から100年の節目を迎える。

インターネットが普及された現代においても、やはり雑誌には雑誌の魅力がある。
店頭に陳列された映画雑誌の装丁は、無性にドキドキ感を与えてくれる。ページをめくれば、映画の写真や解説、監督や役者のインタビュー、評論など、ネットでは味わえない高揚感、直接手にとって見ることが僕たちの想像力をより掻き立ててくれるものなのだ。
展示場には、古きから近年までの日本の映画雑誌が数々展示されていた。
日本で映画が普及され始めたのは明治末期だから、「活動写真界」の創刊が明治42年ということは、日本の映画史とともに映画雑誌は歴史を並走してきたことになる。
この時代において映画雑誌は、映画の情報を知るうえでとても貴重なものだったのだ。
僕の全く知らない映画雑誌たちが並んでいる。
やはり現在42歳の僕の世代が知っているのは、創刊から100年目を迎えた「キネマ旬報」。
僕も「キネマ旬報」のスタンリー・キューブリック、松田優作や北野武の映画が表紙になった号は今でも所有保管している。
「スクリーン」「ロードショー」は兄が毎月買っていた。
「スクリーン」創刊は1946年5月で表紙は原節子さん。
「ロードショー」は1972年5月に創刊、表紙はカトリーヌ・ドヌーブ。
あと情報誌では「ぴあ」、子供の頃はアニメーション誌の「アニメージュ」「アニメディア」「月刊ニュータイプ」もよく購入していた。
歴史ある映画雑誌の数々は、僕世代ではまだ「なつかしい」といった感慨深いものは芽生えず、未知なる昔の歴史資料であった。
戦前、様々な映画雑誌が誕生したようだが、戦争になるとほとんどの映画雑誌が休刊になったようだ。
「キネマ旬報」もカタカナが使用できないから「映画旬報」になった。
戦争が終わるとアメリカ映画一色になり、誌面も華やかになった。
展示されている映画雑誌を見ることで、映画の歴史はもちろん、日本の歴史まで見えてくる。
明治や大正の時代、戦前、戦中、戦後、そして近代へと。
これから映画雑誌はどのようなカタチで残っていくのであろうか。
僕も映画雑誌を購入することはなくなった。
しかし映画雑誌がなくなってほしくないという矛盾がある。
今回の展示ではいつの時代も人々が、映画雑誌を秘かな愉しみとして映画のロマンを膨らませていたんだろうなぁと、思いを馳せるのであった。


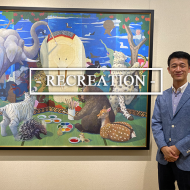
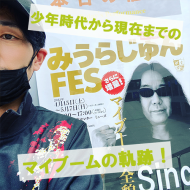

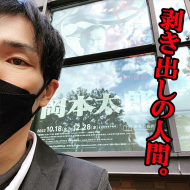
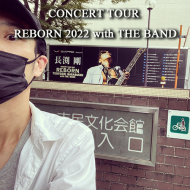



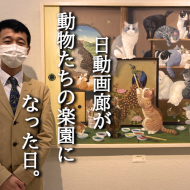
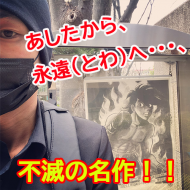
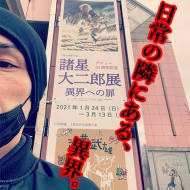
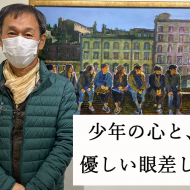

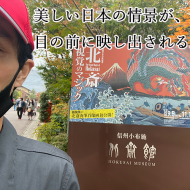



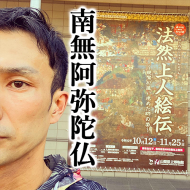
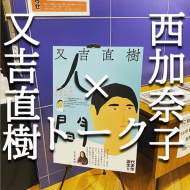
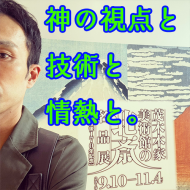

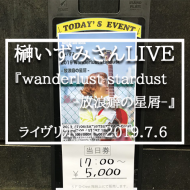


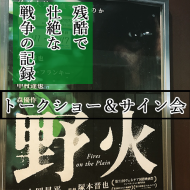



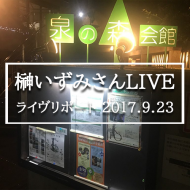



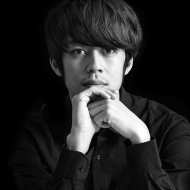

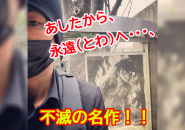

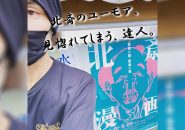
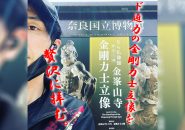

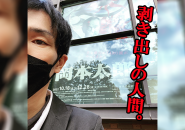
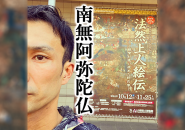


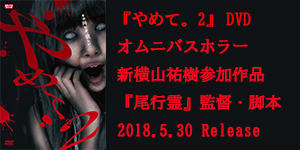

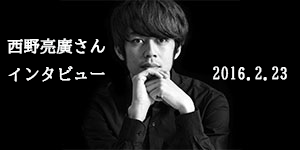


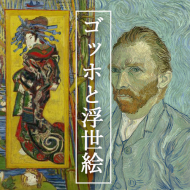

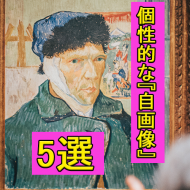
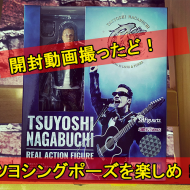

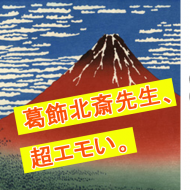
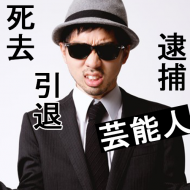

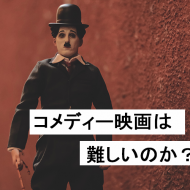

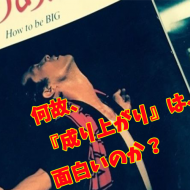
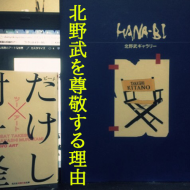

この記事へのコメントはありません。